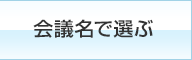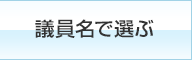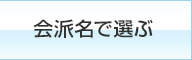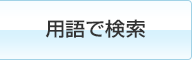録画映像配信
※本会議・委員会の録画映像をご覧いただけます。
- 令和6年第2回定例会 6月10日 一般質問
- 日本共産党茅ヶ崎市議会議員団 今井 理華
eyJwbGF5ZXJLZXkiOiJjYmJlMDljOS0yYzc0LTQwNDEtOWJkNC1iYjZlY2UzYjk0MDAiLCJhbmFseXRpY3NLZXkiOiI5ZWM4YTVlMS1lNWNkLTRkMzUtYTFlMC0wOTE4MWYzOTQwMDYiLCJpc0xpdmUiOmZhbHNlLCJ0aXRsZSI6ImNoaWdhc2FraS1jaXR5XzIwMjQwNjEwXzAwNDBfaW1haS1yaWthIiwicGxheWVyU2V0dGluZyI6eyJwb3N0ZXIiOiIvL2NoaWdhc2FraS1jaXR5LnN0cmVhbS5qZml0LmNvLmpwL2ltYWdlL3RodW1ibmFpbC5qcGciLCJzb3VyY2UiOiIvL2NoaWdhc2FraS1jaXR5LnN0cmVhbS5qZml0LmNvLmpwLz90cGw9Y29udGVudHNvdXJjZSZ0aXRsZT1jaGlnYXNha2ktY2l0eV8yMDI0MDYxMF8wMDQwX2ltYWktcmlrYSZpc2xpdmU9ZmFsc2UiLCJjYXB0aW9uIjp7ImVuYWJsZWQiOiJ0cnVlIiwicGF0aCI6Ii8vY2hpZ2FzYWtpLWNpdHkuc3RyZWFtLmpmaXQuY28uanAvP3RwbD1jYXB0aW9uJnRpdGxlPWNoaWdhc2FraS1jaXR5XzIwMjQwNjEwXzAwNDBfaW1haS1yaWthIn0sInRodW1ibmFpbCI6eyJlbmFibGVkIjoiZmFsc2UiLCJwYXRoIjoiIn0sIm1hcmtlciI6eyJlbmFibGVkIjoiZmFsc2UiLCJwYXRoIjoiIn0sInNwZWVkY29udHJvbCI6eyJlbmFibGVkIjoiZmFsc2UiLCJpdGVtIjpbIjAuNSIsIjEiLCIxLjUiLCIyIl19LCJza2lwIjp7ImVuYWJsZWQiOiJ0cnVlIiwiaXRlbSI6WzE1XX0sInN0YXJ0b2Zmc2V0Ijp7ImVuYWJsZWQiOiJmYWxzZSIsInRpbWVjb2RlIjowfSwic2Vla2JhciI6InRydWUiLCJzZHNjcmVlbiI6ImZhbHNlIiwidm9sdW1lbWVtb3J5IjpmYWxzZSwicGxheWJhY2tmYWlsc2V0dGluZyI6eyJTdGFsbFJlc2V0VGltZSI6MzAwMDAsIkVycm9yUmVzZXRUaW1lIjozMDAwMCwiUGxheWVyUmVsb2FkVGltZSI6MzAwMCwiU3RhbGxNYXhDb3VudCI6MywiRXJyb3JNYXhDb3VudCI6M319LCJhbmFseXRpY3NTZXR0aW5nIjp7ImN1c3RvbVVzZXJJZCI6ImNoaWdhc2FraS1jaXR5IiwidmlkZW9JZCI6ImNoaWdhc2FraS1jaXR5X3ZvZF82MDU3IiwiY3VzdG9tRGF0YSI6eyJlbnRyeSI6InB1YmxpYyJ9fX0=
1 障がい者の就労支援について
(1) 現在行われている施策と課題について
・就労支援、定着支援などの利用状況を問う。
・障がいの種類ごとの定着率向上など、主な課題を問う。
・障がい者法定雇用率達成のため、障がい者と企業とのミスマッチを防ぐなどさまざまな取組が必要と考える。企業からの相談対応、企業へのサポートなどについて問う。
・障がい者本人、家族のニーズの把握方法などを問う。
(2) 課題に対する今後の取組について
・障がいの種類ごとの特徴的な課題に対する今後の取組を問う。
・障がい者法定雇用率は今後、徐々に引き上げられていく。市内企業への周知徹底など対応を問う。
・身体障がい者と比較して精神・知的障がい者は就労率、定着率が低い傾向にある。これを引き上げるための具体的な取組を問う。
2 障がい児・者を看護・介護する家族に対する支援について
(1) 支援の内容、趣旨及び課題について
・学校の長期休暇や放課後の障がい児の居場所確保が家族の心身のケア、就労などのために必要と考える。現状と課題を問う。
・学校などを卒業後に障がい者が通う場所の確保が家族の心身のケア、就労などのために必要と考える。現状と課題を問う。
・障がい児の保護者は申請手続き、面談、相談、見学などで学校や市役所などへ行くことや付き添いなどの必要がある。これにより就労に影響すると考えるが見解が問う。
・家族の就労支援に関するニーズの把握方法などを問う。
(2) 課題に対する今後の取組について
・家族の健康維持、就労支援のために本市のみでできることは限られている。さまざまな団体、近隣の自治体との連携協力など、今以上に必要と考えるが見解を問う。
・県や国に要望していく必要もあると考えるが見解を問う。
(1) 現在行われている施策と課題について
・就労支援、定着支援などの利用状況を問う。
・障がいの種類ごとの定着率向上など、主な課題を問う。
・障がい者法定雇用率達成のため、障がい者と企業とのミスマッチを防ぐなどさまざまな取組が必要と考える。企業からの相談対応、企業へのサポートなどについて問う。
・障がい者本人、家族のニーズの把握方法などを問う。
(2) 課題に対する今後の取組について
・障がいの種類ごとの特徴的な課題に対する今後の取組を問う。
・障がい者法定雇用率は今後、徐々に引き上げられていく。市内企業への周知徹底など対応を問う。
・身体障がい者と比較して精神・知的障がい者は就労率、定着率が低い傾向にある。これを引き上げるための具体的な取組を問う。
2 障がい児・者を看護・介護する家族に対する支援について
(1) 支援の内容、趣旨及び課題について
・学校の長期休暇や放課後の障がい児の居場所確保が家族の心身のケア、就労などのために必要と考える。現状と課題を問う。
・学校などを卒業後に障がい者が通う場所の確保が家族の心身のケア、就労などのために必要と考える。現状と課題を問う。
・障がい児の保護者は申請手続き、面談、相談、見学などで学校や市役所などへ行くことや付き添いなどの必要がある。これにより就労に影響すると考えるが見解が問う。
・家族の就労支援に関するニーズの把握方法などを問う。
(2) 課題に対する今後の取組について
・家族の健康維持、就労支援のために本市のみでできることは限られている。さまざまな団体、近隣の自治体との連携協力など、今以上に必要と考えるが見解を問う。
・県や国に要望していく必要もあると考えるが見解を問う。